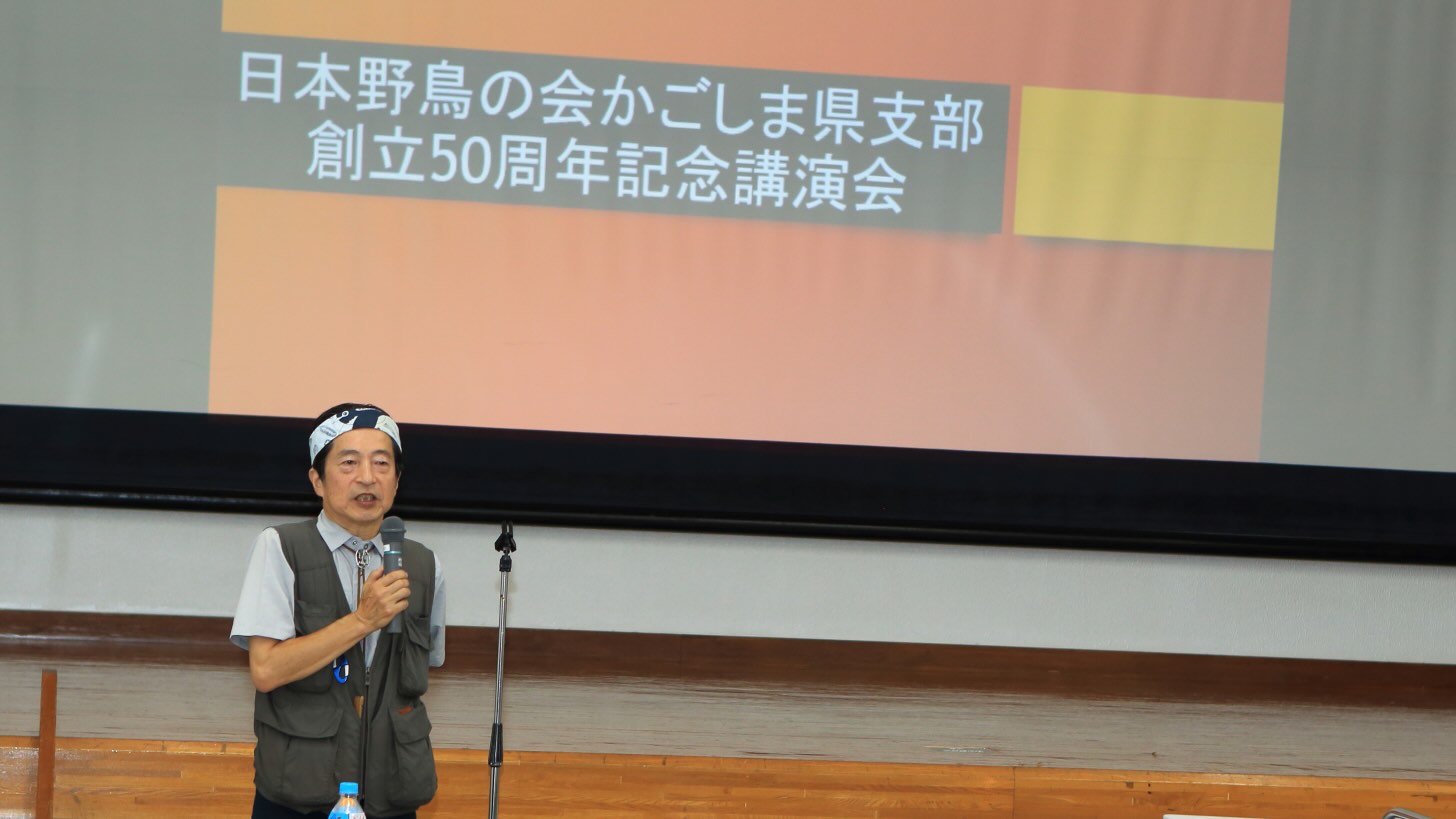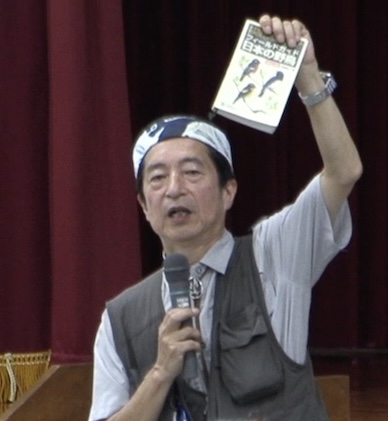★ ハトの水飲み
西田橋下の水路で水を飲むドバトについて、人間はおっぱいを吸うことで下を向いても水を吸い上げて飲むことができます、野鳥は人間のようには元々飲めません。口に含んで上を向いて水を自然に下へ流し込むことしかできません、しかしハトだけは下を向いて人間と同じように飲む能力があります、理論的なことはまだ分かっていません。
★ ハクセキレイの親子
しばらく歩くとハクセキレイの親子数羽がいました。そこで、ハクセキレイは尾羽の長さで成長の段階が判断できます(短い方が若鳥に)、親と同じ長さになるのに巣立ってから1ヶ月程度と説明され、成長の段階が推測できます。また巣立ち後の親の給餌時期は1ヶ月弱とのことです。スズメの給餌期間は一番早くて10日程度だそうです。
近くにいたキジバトの親?子?の見分け方は、首の付け根に縞模様があれば親で、幼鳥にはないそうです。
★ セキレイ類の尾羽
セキレイ類が尾羽を上下にフルのはどうしてですか?と質問がありましたが、現時点での研究はされておらず判明してません。ただ考えられるのは、開けた広い場所に居るので敵(猛禽など)に対し「あなたが私を狙ってることには気付いていますよ!」のアピールではないかと話されました。

★ サギ類は飛びながらフンをする
一般的に鳥はフンをする時は尾羽を上にあげてしますが、サギ類は飛びながらすることがよくあります。飛翔中に尾羽を上にあげることはできないのにフンをします。サギ類は両足を閉じて飛んでいますが、フンをする時は両足を広げて体に飛び散らないようにしてフンをするそうです。その場面写真を紹介してもらい、その様子がよくわかりました。
★ さえずりの話
野鳥の囀りの質問があり、基本的にメスが鳴くことはなくオスだけがメスの気を引くために鳴きます、ただし危険を感じた場合にはメスも鳴くことがあると言われていますが、実際に聞くことは無いと考えてください。
小鳥が囀ることで英語では「Song Bird」と表現するそうです。また恐竜から進化した野鳥は体の構造は恐竜と同じで、木の上で生活するようになり、木の葉などでお互いの姿が確認できなくなり囀りや鳴き声を発するようになった。歌わない鳥はヒヨドリとカラスだけとの話もあった。